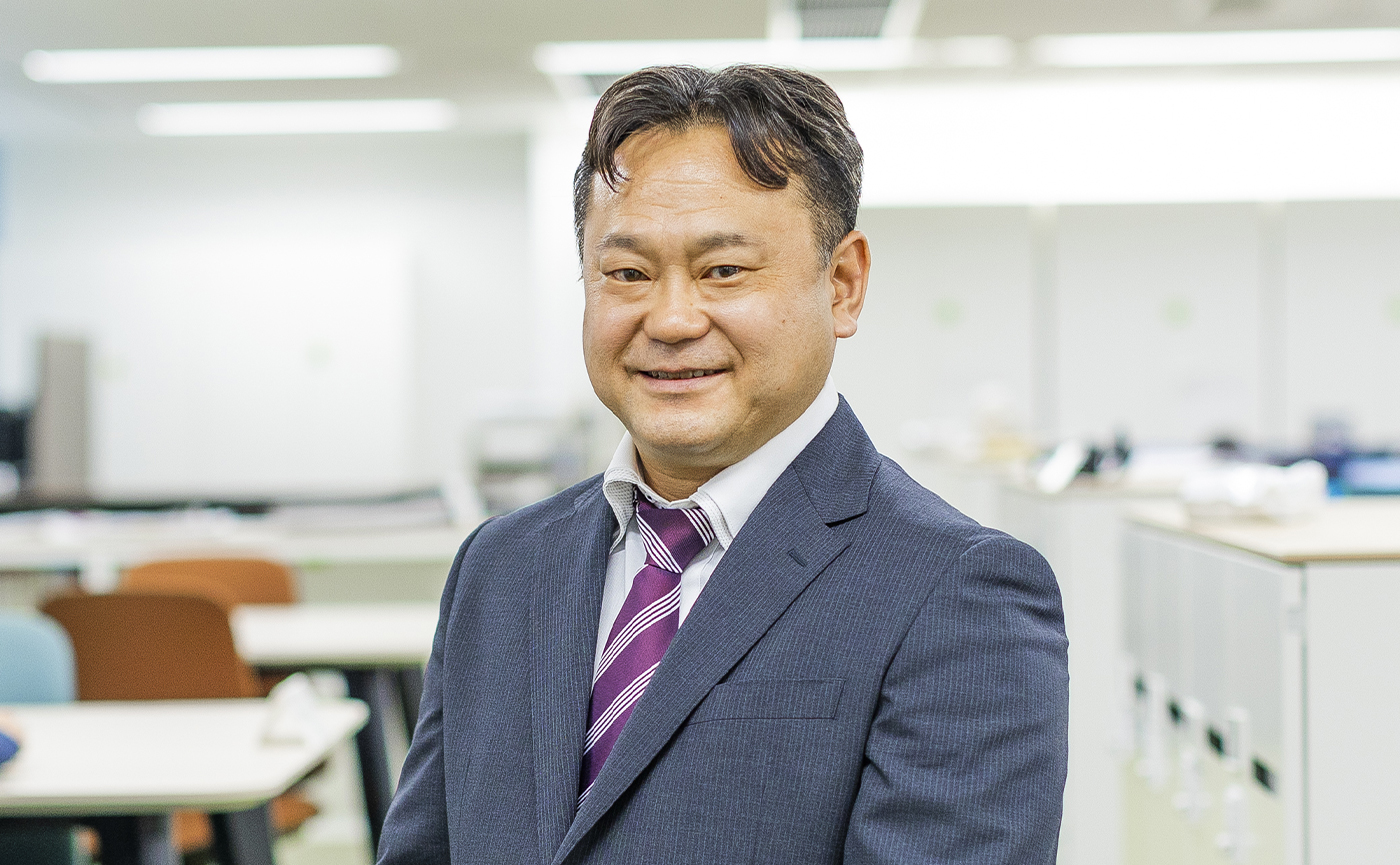
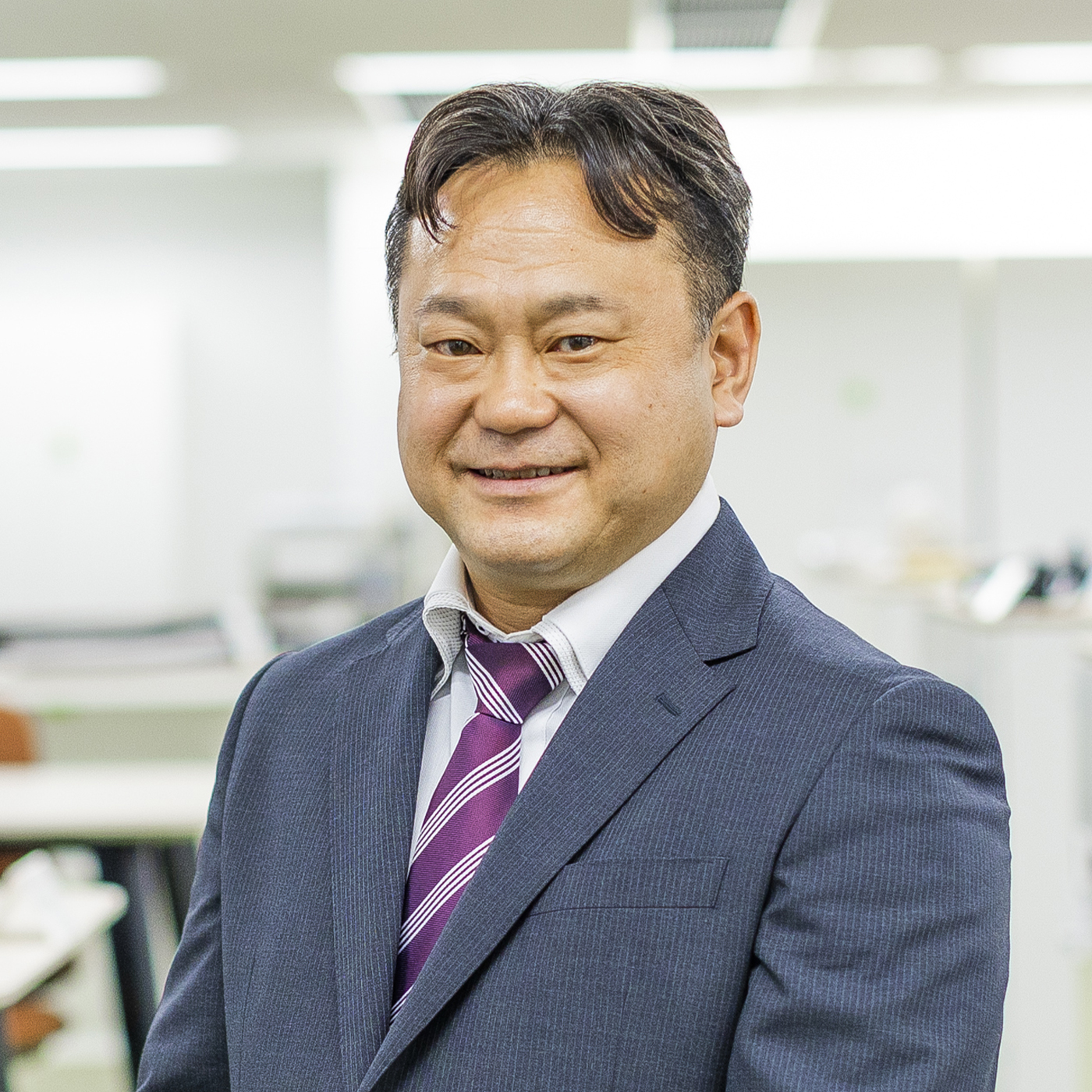
設計図よりも
人と向き合ってきました。
設計図よりも
人と向き合ってきました。
初めて熱い議論を交わした日々が、自分の原体験です。
入社は1998年です。それから随分年月が経ち、その間多くの業務に関わってきました。もともとは、学生時代から街づくりに興味があったんです。いわゆる「地図に残る仕事」をしたいと思って、大学では都市計画の研究室にいました。一つの都市の将来プランを5年、10年といったスパンで考え、その中に自分のアイデアを活かせるところが好きだったんです。
私が入社した当時は、会社として都市計画事業に力を入れている背景があって、入社後は都市計画の業務を担当していました。残念ながら現在は都市計画から離れてしまいましたが、そこでの経験が私の原体験になっています。「街づくりに自分のアイデアを活かしたい」と意気込んで挑んでみたものの、現実は難しいことだらけでした。街の未来をプランニングするために住民の方の意見を聞こうと、何度も意見交換会を重ねます。でも住民の方からすれば、いきなり外からやってきた新人のコンサルタントと本気で向き合う訳がありません。殆どの方が最初のうちは「私は何十年ここに住んでいるが、君はこの街のことをどれだけ分かっているのか」とあまり相手にしてくれません。そうすると私も悔しいですから、それこそ、平日・休日問わずその街を歩き回り、自分なりに一生懸命勉強して話し合いに臨むようになります。そうすると少しずつ熱意が伝わり、関係が近づいていくから不思議です。ついには、お互いが本音の意見をぶつけあえるようになり、そこで初めて、計画や設計という具体的なプランが生まれるんです。この過程こそが仕事の面白みなんじゃないかと、その時に初めて気づきました。
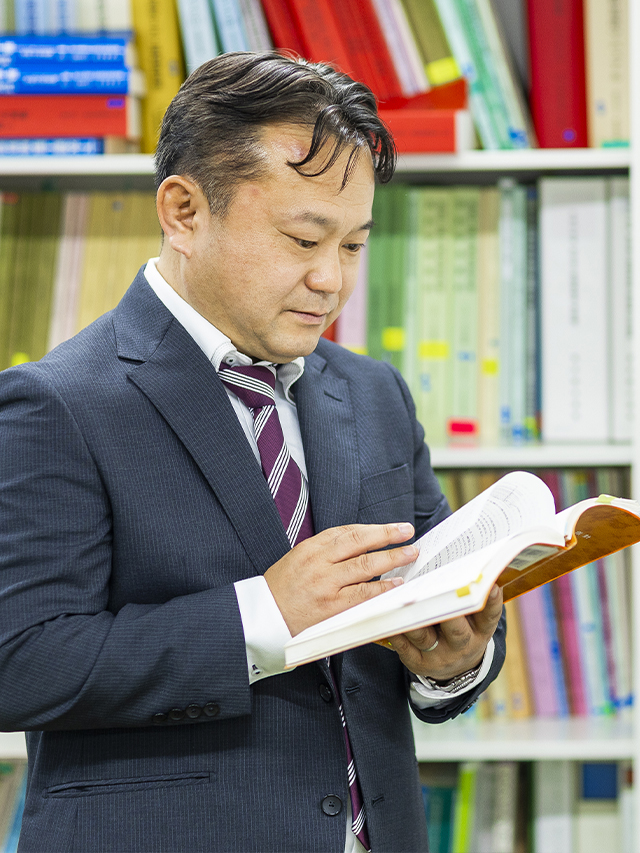
目の前の相手と向き合う時間こそが、やりがいだと感じています。
担当業務が都市計画から道路やトンネルの設計に変わっていっても、果たす使命は同じです。一つの都市を考えることと、都市の中の、どこにどうやって道路やトンネルを通すのかということ。思考の範囲がよりミクロなスケールになっただけで、「こうしたい」という目的に向かって自分のアイデアやイメージを活かしていく面白さは同じだと感じています。そして、大事にしたいと思っていることも、同じです。
お客様には「こうしたい」というイメージがあります。それは具体的なイメージの時もあれば、漠然としたイメージの時もあります。そのイメージに対して、私は「これが最適なんじゃないか」という専門家としての考えを取り入れ具体化していくのですが、互いの考えが最初からピッタリ重なることって、滅多にありません。だから、話し合うんです。どんな最終形をイメージしているのか。イメージしているものが本当につくれるのか。無理すればつくれるとしても、本当にそれがこのケースにおける最適解なのか。お互いが思う正解を出し合いながら、少しずつ考え方の溝を埋めていきます。設計者として大切なのは、都市計画も道路設計も答えは一つではないという考えと、本当に施工ができるのかという視点を持つことです。そうした話し合いを繰り返してようやく、同じゴールを見られるようになると思うんです。あえて言葉にしてしまえば、これって、この仕事のすごく面倒くさい側面だと思います。でも自分にとってはこの、目の前の相手と向き合う時間こそが、やりがいだと感じています。思い返してみると物事がスムーズに進んだ仕事って意外に思い出に残っていないんです。それよりも「あの時は合意するまでにすごく時間がかかった」とか「目的を共有するまでにこんな議論をした」とか、苦労した経験ばかりが頭の中に浮かんできます。やっぱり、大変な思いをした仕事ほど思い入れが強いです。


BIM/CIM室長として、若手の育成にも力を入れています。
いまは、CIMに取り組んでいます。これは私たちの会社だけではなく業界全体の課題とも言えるのですが、今後は2次元の図面から3Dモデルを使った設計への移行が必須になってきます。3Dモデルだと何がいいのか、たくさんの利点があるので全ての説明は難しいのですが、大きくは、設計段階から現地の状況を詳細に反映したり、今まで見えにくかった3次元的な干渉や複数図面の整合性が確認できたりとより正確な図面がつくれること。そのために、施工段階に入っても設計段階の想定とズレのない工事が可能になり、効率的な施工が可能になることがあげられます。私が入社した頃の設計図は、手書きで作成していました。そこからあっという間に、CADでの製図に置き換わったように、今後は3D設計が当たり前になる時代がそこまで来ています。今までは2次元設計の成果を基に3Dモデルを作成していましたが、今後は3Dモデルから2次元図面を切り出すことになります。そのために、当社でも3D設計を仕事に取り入れることは当然として、社内での技術の普及や若手育成を進めています。

採用情報を深堀る
選考へのエントリー方法や入社までの流れについて。
